[AI新規事業創出]Qualitegが考える、企画後にもめないための新規事業承認判断軸の検討方法とは
新規事業の検討において、クライアントからの相談は手段ありきで始まることが多く、DXやAI導入の提案が役員から承認されないケースが多いです。事業化の承認を得るためには、なぜその事業を自社で行う必要があるのか、その目的とゴールを明確に設定することが重要です。
![[AI新規事業創出]Qualitegが考える、企画後にもめないための新規事業承認判断軸の検討方法とは](https://images.unsplash.com/photo-1619344501177-cb47c4a94c59?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDF8fGRlY2lkZXxlbnwwfHx8fDE3MTMwMjQ1MDN8MA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)
Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
新規事業検討を担当させていただくクライアントからよくご相談を受ける件があります。
これ(例えばDXなど)で新規事業を検討してと言われたのに、なぜか役員からNGが出ちゃうんですよ。
というお声を多く耳にします。AI導入してとか、DX考えてなど、手段ありきで新規事業検討を開始されるケースは多いと思いますが、新規事業案としてそのソリューションを提示しているのになぜか、事業化の承認をされないというお悩みを抱えてらっしゃる方が多いです。

今日は、その新規事業はなぜ今企画すべきか、どうしたら事業責任者の承認がスムーズにいただけるのかという観点でお話ししたいと思います。
まず考えるのはなぜその新規事業を始めるのか
新規事業を企画する際に一番重要なのは「なぜその新規事業を自社でやる必要があるのか」という問いに自信をもって答えることが必要です。
新規事業のコンサルティングをお受けする際に私が必ずクライアントに質問させていただくのが「なぜ今回自社で新規事業を検討されているのか」という質問です。だいたいの方が「役員にDX考えてと言われたので」「他社がAI始めたらしいのでうちもAIやらないと」という形で、ソリューションは確定しているけれども、事業をやる意義が不明瞭な場合が多いのです。
そのため、他社がやっていそうなDX案件を模倣して自社でもやりましょうと安易に提案してしまい、事業化承認が下りない、そのようなケースが多いと思います。
今日はなぜ、その新規事業を自社が始める必要があるのか、を考えながら、何がOKなら、事業化OKの判断になるのか、を解説していきたいと思います。
イノベーションの真価は、異なる強みが融合することで生まれるシナジーにあります。株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、企業の強みと外部リソースの最適な組み合わせによる革新的シナジーを創出するプログラム。企業の現状分析を通じて核となる強みを明確化し、それを補完・増幅する外部パートナーを戦略的に選定します。

アイデアワークショップやハッカソン企画を通じて「自社だけでは生み出せない」化学反応を促進し、オープンイノベーションやパートナー開拓で持続的な共創関係を構築。最先端AI技術の活用も含め、経験豊富な専門コンサルタントが、この革新的シナジーを最大化するプロセスを設計し、1+1が3以上になる価値創造を実現します。強みと強みが出会うとき、革新は加速します。
自社で新規事業を始める意義とは
まず初めに、自社が新規事業を実施する目的を明らかにしましょう。
- 市場の拡大
- 収益源の多様化
- イノベーションの推進
- 顧客ニーズへの対応
- ブランドイメージの強化
- 戦略的パートナーシップの構築
- 新UX創出
- 社会貢献
- 人財育成
新規事業を実施するにあたり、だいたいのケースはこの上記の項目に当てはまると思いますが、企画担当者と事業承認者の認識相違があるケースが多く見受けられます。
これらを参考にしていただき、まず初めに、なぜ今回新規事業を企画する必要があるのかを言語化して認識合わせをするところから始めましょう。
事業目的のゴールを設定する
新規事業実施の目的が決まったら、次にその事業目的のゴールを決めます。
ここでは例えば「市場の拡大」が事業目的であれば、「市場導入後3年で売上規模10億円達成をゴールとする」ですとか、「新UX創出」であれば、「自社のターゲットユーザーである都市部で働くビジネスマンの生活充実度を向上させるサービスを市場導入することをゴールとする」、「ブランドイメージの強化」であれば、「自社のサービス導入後、記事化され、自社サイトの訪問者数が現状より20%アップしたことをゴールとする」など、事業目的により、そのゴールを決めることができます。

まずは目的とゴールの設定を
旅行で例えるなら「仕事の疲れを癒して心身ともにリフレッシュしたい」という目的が決まり、「1泊2日ですぐに東京に帰ってこれること」を条件とすれば、「箱根の温泉に行こう」=東京近郊でリフレッシュするところに旅行に行くと決めることができますよね。
新規事業の方向性検討も同じなのです。
目的とゴールを最初にクリアにしないでみなさんお話を初めてしまわれるケースが多いです。
旅行で例えていうなら、「ニューヨークに行こう」、「ハワイの方がいい」、「九州に温泉に行こう」、「いいえ、北海道にゴルフに行きましょう」など、話が全くまとまらないのと同じです。新規事業を検討される際はまず、目的とゴールをクリアにしましょう。
事業目的が決まると新規事業の方向性アイディアが見えてくる
さて、事業目的が決まると、自社がどのような方向で事業をすべきか見えてきます。
ここでは例として先ほどの
「新UX創出」であれば、「自社のターゲットユーザーである都市部で働くビジネスマンの生活充実度を向上させるサービスを市場導入することをゴールとする」
をテーマに検討してみましょう。
アイディア出しをする前に、自社の保有するユーザー群の調査として、インタビュー調査やアンケート調査をしたりする必要がありますが、そのターゲットを決めるために、ざっくりした方向性のアイデアを決めるのがこのタイミングです。

ここでは、例として、都市部で忙しく働くビジネスマンの生活充実度を向上させるサービスの方向性として以下を検討してみます。
- オフィスや自宅などで健康維持ができるサービス
- 仕事の疲れをとり、リフレッシュできるサービス
- 自身のキャリアアップのためにサポートができるサービス
役員(=事業責任者)と握るべき事業化判断のクライテリアは
企画案が出た後に事業化判断を事業責任者である役員の方にしていただきますが、その前にどういう案件、方向性、検討のアプローチをするので、このような判断軸で承認してもらいたいとお伺いを立てる必要がありますよね。
そのために、現段階で、アイディアの方向性を出し、新規事業の目的とゴールを設定して、事業化判断のクライテリアについて提案してみましょう。
例えば今回であれば
自社の電気自転車サービスを愛用してくださっている、都市部のビジネスマンをターゲットにして、今回は自社の強みであるユーザーパーソナライズ情報などを活かした事業展開を考えています。
たとえば、方向性としては、オフィスや自宅などでもできる健康維持ができるサービスや、仕事の疲れが取れるリフレッシュできるサービス、自身のキャリアアップのためのサポートができるサービスなどを考えたいと思っています。
新規事業の事業化検討にあたり、以下3点を事業化判断のポイントとしたいので、今回はこの判断ポイントについてご承認をお願いします。
- 日本ではまだ大手が参入していないが、市場ニーズがあり、成長が見込める市場であること
- 自社の強みを活かしてビジネスシナジーを創出し、他社との差異化が図れるサービス案であること
- 今年度中にサービスを市場導入できること
このような形で最初に事業承認者と握るべき項目は、アイディアの良し悪しではなく、事業化の目的と何をもって事業化Goの判断をするか、という基準を決めて合意することが重要です。
このフェーズはやり慣れてない、面倒くさいなどと懸念される方が非常に多いのですが、最初に方向性を合わせないと、変な旅行先を提案してしまうのと同じですので、最初に目的とゴール、判断ポイントのすり合わせを致しましょう。
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
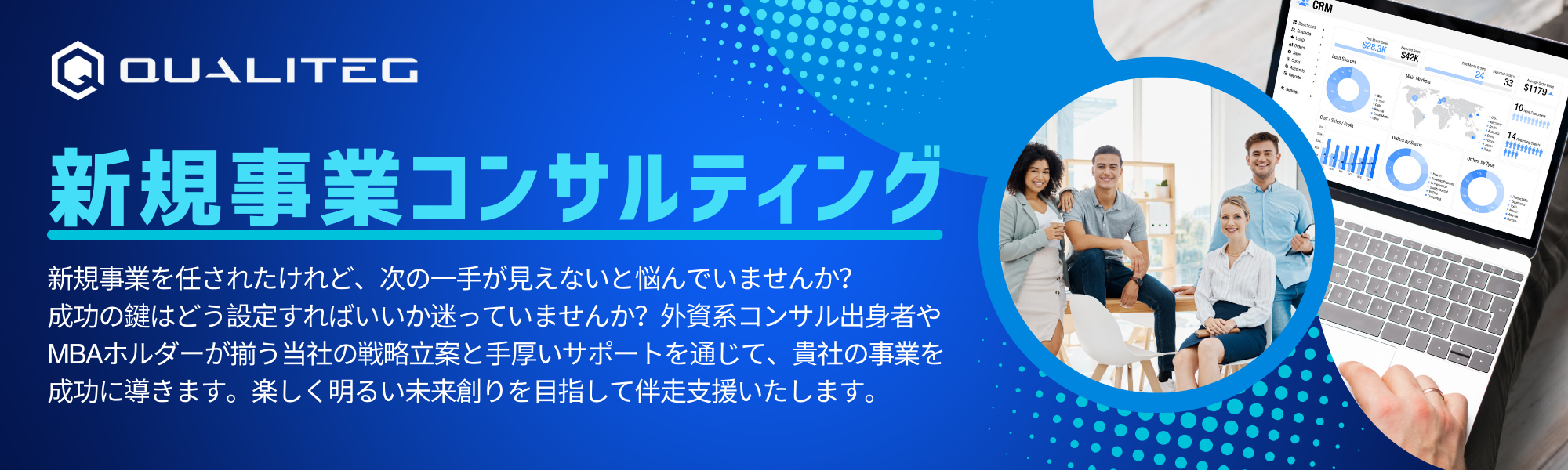
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。次回のコラムも、ぜひご期待くださいね。
navigation





