Qualitegセレクション:アイディア深堀編②6W2Hの活用術

Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
本日のテーマは6W2H
Qualitegセレクションは、ユーザーエクスペリエンス(UX)向上のためのヒントやツールを紹介するシリーズです。今回は、アイディアをより具体的に、実行可能なレベルまで深堀りする手法として、6W2Hの活用術をご紹介します。
優れたUXを実現するには、ユーザーのニーズを深く理解し、それを満たすサービスやプロダクトを提供することが不可欠です。そのためには、アイディア段階で徹底的に検討し、実現可能性や課題を明確にする必要があります。
今回は、アイディアを深堀りする際に非常に役立つツール「6W2H」について詳しくご紹介します。
6W2Hとは?
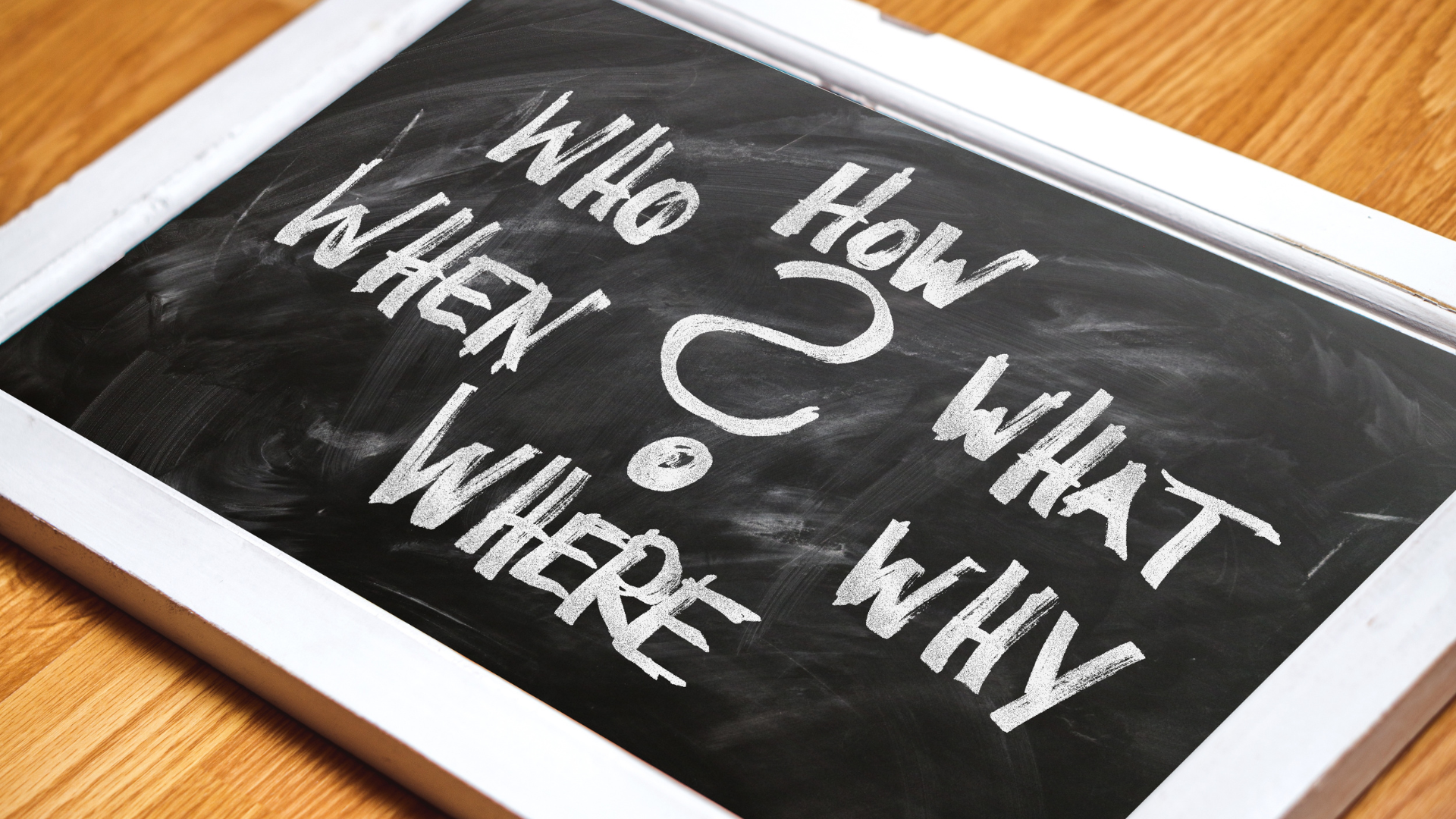
6W2Hは、問題解決や状況分析のための強力なフレームワークです。以下の8つの質問から構成されています:
- Who(誰が)
- What(何を)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
- How much(いくら)
- How many(どのくらい)
これらの質問を使うことで、アイディアや問題の本質に迫ることができます。
(中学時代の英語の授業を思い出しますね~^^)
6W2Hの活用方法

- アイディアの具体化
新しいアイディアが浮かんだら、6W2Hの質問を順番に適用してみましょう。例えば、「オンライン料理教室を始める」というアイディアの場合:- Who:誰が教えるのか?誰が受講者になるのか?
- What:どんな料理を教えるのか?
- When:いつ開催するのか?頻度は?
- Where:どのプラットフォームを使うのか?
- Why:なぜオンライン料理教室が必要なのか?
- How:どのように進行するのか?
- How much:受講料はいくらにするのか?
- How many:1回あたりの受講者数は何人にするのか?
- 問題点の洗い出し
既存のプロジェクトや製品の問題点を見つける際にも6W2Hは有効です。各質問に答えることで、見落としていた課題が浮かび上がることがあります。 - 計画立案
新規プロジェクトの計画を立てる際、6W2Hを使うことで漏れのない綿密な計画を立てられます。 - 情報収集
調査や研究を行う際、6W2Hを念頭に置くことで、必要な情報を漏れなく収集できます。 - プレゼンテーションの構成
6W2Hに基づいてプレゼンテーションを構成することで、聴衆に分かりやすく情報を伝えられます。
株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、革新創出のプロセスを明確化する共創支援プログラムです。私たちのアプローチは、4つのステップで構成されています。まず企業の現状を徹底分析し、次に外部との協業による価値創出の戦略を策定。さらに具体的なロードマップとKPIを設定し、最後に実行を強力に支援します。

アイデアワークショップ、ハッカソン企画、AI技術活用など、多彩なサービスメニューを通じて、革新創出の各段階を確実に推進。経験豊富な専門コンサルタントが伴走し、「自社内だけでは難しい」革新を、外部との協業によって実現する道筋を明確に示します。
6W2H活用のコツ

質問の順番にこだわりすぎない
- 状況に応じて、最適な順序で質問を使いましょう。司会進行の自分はこの順番にシートを埋めながら話をしたくなってしまうのですが、せっかくみんなからいろんなアイディアが出てきているので、ランダムにシートを埋める懐の深さでファシリテーションをお願いします★
深掘りする
- 各質問に対して、さらに「なぜ?」を重ねることで、より本質的な理解が得られます。最初はちょっと恥ずかしくても場に馴染んでくれば、途中から他のメンバーから発言者に対して「なぜ?」と問うてくれるので、まずは場を温めるつもりで、「なぜ?」を連呼してみてください★
チームで活用する
- 複数の視点から6W2Hを適用することで、より多角的な分析が可能になります。深堀のための「なぜなぜ」にみんなが慣れてくると、嫌な感じで突っ込まれているのではなく、自分の思考を掘り下げるためにあえて壁打ちしてくれているんだね、というような愛情に似た雰囲気が出てくるケースもありますので、ぜひそのような雰囲気になるようにファリシテートしてみてくださいね★
実践例:新商品開発での6W2H活用
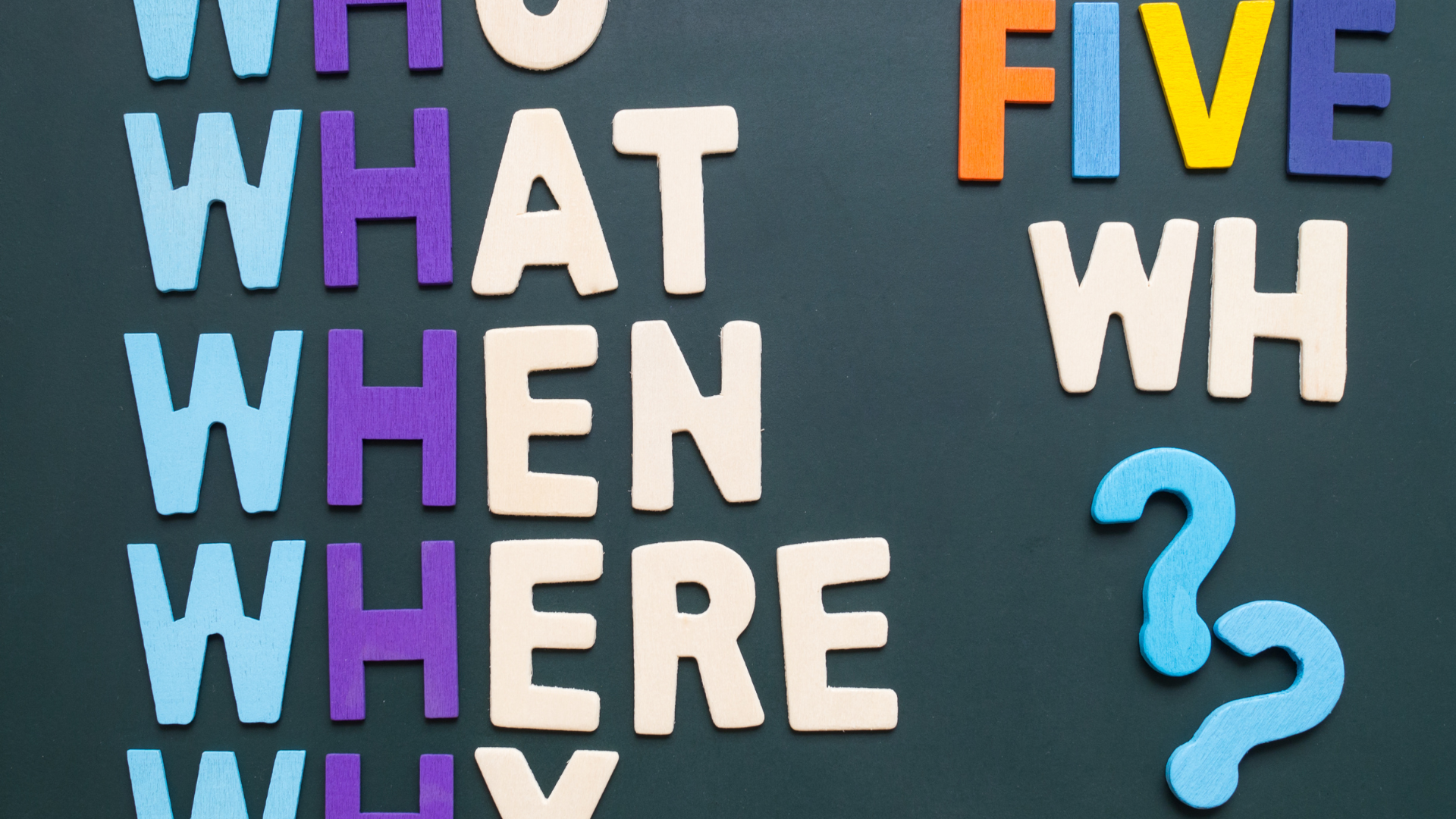
ここでは、6W2Hを実際の新商品開発に適用した例を見てみましょう。「スマート歯ブラシ」の開発を考えているとします。
- Who(誰が):
- 使用者:忙しい社会人、テクノロジーに興味がある人
- 開発者:当社の技術チームとデザインチーム
- What(何を):
- スマートフォンと連携し、歯磨きデータを記録・分析する電動歯ブラシ
- When(いつ):
- 開発期間:1年
- 発売時期:来年の歯の衛生週間に合わせて
- Where(どこで):
- 販売チャネル:自社オンラインストア、家電量販店、ドラッグストア
- Why(なぜ):
- 歯の健康への意識向上
- 効果的な歯磨き習慣の形成支援
- How(どのように):
- Bluetooth接続でスマートフォンアプリと連携
- AIによる歯磨きパターンの分析と改善提案
- How much(いくら):
- 販売価格:15,000円
- 開発予算:5,000万円
- How many(どのくらい):
- 初年度販売目標:10万台
この例からわかるように、6W2Hを使うことで、新商品のコンセプトから具体的な開発計画まで、幅広い側面を網羅的に検討することができます。
企画経験が浅い方は自分の言いたいことがなかなか伝えられない、資料に書いていることと、口頭で補足していることが全然違うなどというケースもあるので、上司に突っ込まれる前にまずはこのフレームワークを使って、自分自身と壁打ちしてみてください。(ご要望あればMicheleも1時間からスポット壁打ちできますので、お問い合わせフォームまでご連絡くださいませ★)
6W2H活用の注意点

- 過度な詳細化を避ける:
初期段階では、大まかな方向性を定めることに集中し、細部にこだわりすぎないようにしましょう。 - 柔軟性を保つ:
6W2Hで得られた答えを絶対視せず、状況の変化に応じて適宜見直す姿勢が重要です。 - チーム全体での共有:
6W2Hの結果を関係者全員で共有し、共通理解を形成することが成功の鍵となります。
あまりくどくど「なぜ?」を言い続けると、ちょっと雰囲気が悪くなるケースもありますがそれは言い方次第ですので^^、ファシリテーションされる方は幼稚園児に話しかけるような優しい気持ちを持ちながら、「それはなぜでしょうか?」みたいに聞いて、責め立てるように「なぜ!?」と聞かないようにご注意くださいね。
まとめ
6W2Hは、アイディアの深堀りや計画立案において非常に有効なツールです。単純な質問の組み合わせですが、これらを丁寧に検討することで、より具体的で実行可能なプランを立てることができます。
日々の業務や新しいプロジェクトに取り組む際は、ぜひ6W2Hを活用してみてください。アイディアの質が向上し、より効果的な問題解決や創造的な発想につながるはずです。
6W2Hは、アイディアの深堀りや問題解決に非常に有効なツールです。シンプルながら強力なこのフレームワークを活用することで、より具体的で実行可能なアイディアを生み出すことができます。ぜひ、日々の業務やプロジェクトで6W2Hを試してみてください。
Qualitegは、これからも皆様のビジネスやプロジェクトの成功を支援するツールや方法論をご紹介していきます。次回もお楽しみに!
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
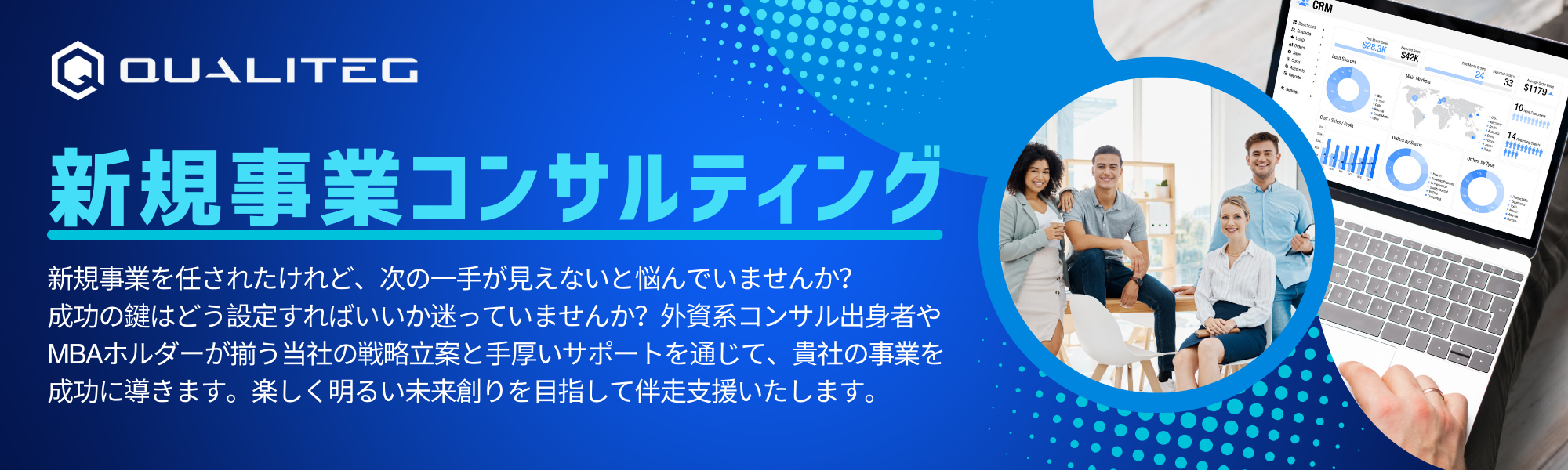
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。






