[AI新規事業創出]Qualiteg流、顧客課題仮説探索インタビューをベースにした顧客課題設定とは
新規事業開発のコンサルティングにおいて、多くの方がすぐにアイディア出しを行いたがる傾向にあります。実際は顧客の課題を把握し、ファクトに基づいたアプローチが質の高い企画につながります。このプロセスには顧客のニーズの再確認、インサイトの抽出、そして「How Might We」というフレームワークを用いた課題の発散が含まれます。
![[AI新規事業創出]Qualiteg流、顧客課題仮説探索インタビューをベースにした顧客課題設定とは](https://images.unsplash.com/photo-1512758017271-d7b84c2113f1?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDJ8fGJ1c2luZXNzJTIwcHJvYmxlbXxlbnwwfHx8fDE3MTM3MDA3MzV8MA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)
Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
新規事業開発のコンサルティングさせていただいている中で、皆さんやはり、アイディア出しをすぐにやりたいと焦っておられる方が多いです。
しかし、そのアイディアを出すために、顧客が何を課題としているか、ファクトをもとに考えていく必要があります。
本日は、顧客の課題をどのように考え、選定していくか、そして本取組で着目し、解決すべき課題を仮説をどうやって検討するべきかという手法についてお話させていただきたいと思います。
まずは、問いの確認を実施する
初めに検討すべき項目は「問いの確認」です。アイディア出しの前に、調査などで発見した問題やニーズの再確認をしましょう。
ここでは、顧客インサイトの抽出方法について解説します。

電気自転車レンタルサービスを例に考えてみましょう。
例えば、
電気自転車をレンタルしたいと思って借りてみたが、充電された電気量が少なかった
というファクトがあったとしましょう。
そのファクトから顧客のインサイト(=こういう状態だったらいいのになと思う状態や、不安材料などの心の声)を想像して書いていきます。
この場合
もっと電気があったら、1回のレンタルで目的地まで行けるのになあ
途中で電気がなくなったら、自転車が重くなって動かなくなるのではないのだろうか
このようなユーザーの心の声が聞こえてくると思います。それらをユーザーの「問い」であると認識しましょう。
株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、イノベーション共創の全プロセスをカバーする総合支援プログラムです。企業の現状分析に基づく精緻な戦略立案から、実行計画の策定、オープンイノベーションやパートナー開拓の実践、そして成果の評価・改善まで、革新創出の全工程を一貫してサポート。

アイデアワークショップ、ハッカソン企画、AI技術活用など、多彩なサービスメニューを通じて、「自社だけでは実現困難」な革新を、外部との協業によって確実に実現します。戦略と実行の両面で豊富な経験を持つ専門コンサルタントが、御社のイノベーション創出を総合的に支援し、社内外の知恵を融合させた新たな価値創造へと導きます。共創イノベーションのワンストップ・ソリューションを、ぜひご活用ください。
次は問いの発散をしてみましょう
ここではHow Might Weというデザインシンキングの問いを定義するフレームワークを活用します。
「How Might We」を日本語に訳すと「どのようにして私たちは〜できるか」となります。しかし、直訳だとなかなかイメージがわかないので、Qualitegでは以下のようなフレームワークとして活用しています。
どうしたら、我々は 「誰」 の為に、「何」を実現してその課題を解決や改善をすることができるだろうか。
このフレームワークに当てはめて「問いの発散」をしてみましょう。
「どうしたら我々は、いつも自社サービスを使ってくださっているユーザー向けに、遠くの目的地までレンタル電動自転車を使ってもらうことができるのだろうか。」
「どうしたら我々は、初めて自社サービスを使いたいと思ってくださる顧客向けに、途中で電気がなくなったら自転車が重くなって動かなくなるのではないかという不安を取り除くことができるのだろうか」
このような形で、顧客インタビューの結果などのファクトをもとに、顧客の課題を出すことができます。
ここがポイントですが、このフェーズでは課題の良し悪しは判断する必要はなく、たくさん課題を抽出することを目的としております。次のフェーズでその課題のうちどの課題を選び、自社の解決策としていくべきかを考えていきましょう。
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
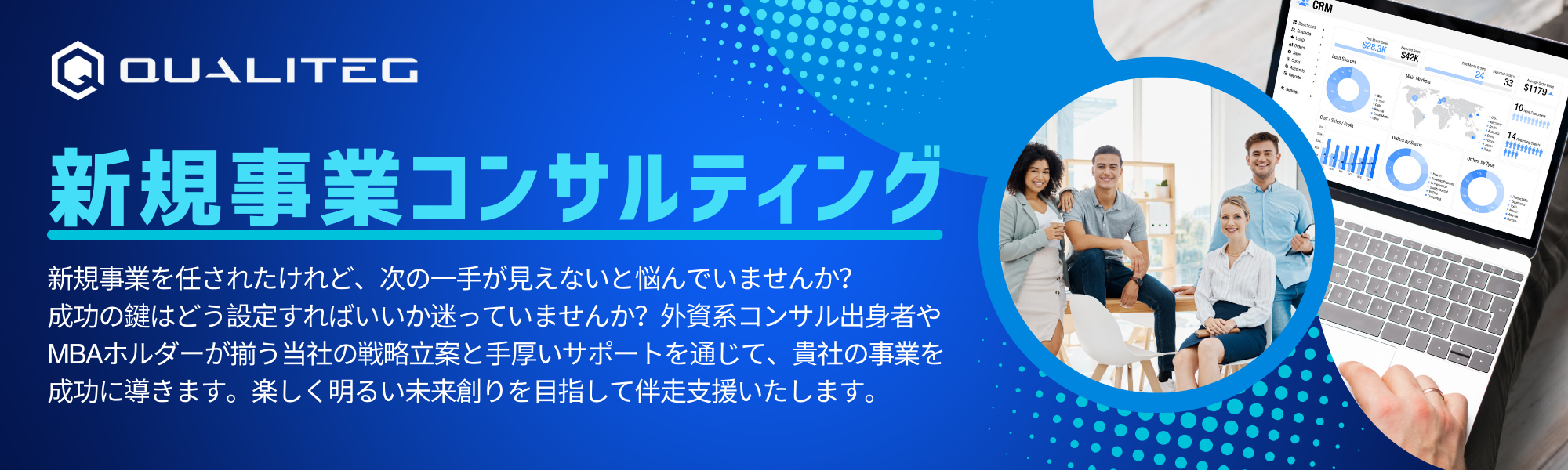
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。次回のコラムも、ぜひご期待くださいね。
navigation





