[AI新規事業創出]Qualitegが考える、アイディア創造フレームワークを利活用する理由
![[AI新規事業創出]Qualitegが考える、アイディア創造フレームワークを利活用する理由](https://images.unsplash.com/photo-1508004680771-708b02aabdc0?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDJ8fGZyYW1lfGVufDB8fHx8MTcxMzcwMTQ2NHww&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)
Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
アイディア創造を成功させるための体系的アプローチ
「新規事業のアイディアが浮かばない」「ブレインストーミングを行っても成果が出ない」というお悩みをよく耳にします。多くの企業コンサルティングを手掛けてきた経験から、アイディア創造の失敗パターンとして最も多いのが「準備なしの突発的なブレスト」です。事業目的やターゲットユーザーを明確にしないまま思いつきで意見を出し合い、結果的に有効なアイディア創出に至らないケースが多発しています。
今回は、Qualitegが提唱する「アイディア創造フレームワーク」について解説します。思いつきではなく、体系的なアプローチで新規事業開発を成功させるためのメソッドをご紹介します。
アイディア創造の第一歩:ターゲットユーザーの明確化
新規事業開発において最初に行うべきステップは「誰に商品やサービスを提供したいか」の明確化です。ペルソナ設計や顧客セグメンテーションを行い、ターゲットユーザーが抱える課題やニーズを正確に把握することが重要です。
ターゲットユーザーはどのようなことを考えているかを理解し、仮説課題やニーズの確からしさを確認する必要があります。
これらは以前お伝えしましたエンパシーマップを活用していただくことが多いのですが、その前にアンケートなどの定量調査やインタビューなどの定性調査を通じて、自社の事業領域に合ったターゲットセグメントを確認し、対象を詳細にイメージする必要があります。
この段階では、以下の調査手法が効果的です。
- 定量調査(アンケート、市場調査データ分析)
- 定性調査(ユーザーインタビュー、フォーカスグループ)
- エンパシーマップの活用(ユーザー心理の可視化)

なぜターゲット設定が重要なのでしょうか?新規事業であっても、既存の顧客基盤や販路と大きく異なるターゲットを設定すると、マーケティング効率が低下し、ユーザー獲得が困難になります。したがって、自社の既存サービスを利用しているユーザー層に向けた新サービス開発が、効率的な新規事業展開の一手法と言えるでしょう。
その理由として、自社の新規事業だからと言って、対象ユーザーや販路が異なる場合、なかなか市場投入後もユーザーを獲得するのが難しいというのが理由です。ですから、現状の自社の有力サービスを使ってくださっているユーザー向けに新しいサービスを提供するのが、新規事業開発の一つのメソッドであると考えているため、この方式をお勧めしております。
イノベーションは、机上の空論ではなく、実践を通じて実現するものです。株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、「実践」にこだわる共創支援プログラム。企業の現状分析に基づく戦略策定はもちろん、その先の「実行」に重点を置いたサポートを提供します。アイデアワークショップ、ハッカソン企画、AI技術活用など、具体的なアクションを通じて社内外の知恵を融合させ、「自社だけでは実現困難」な革新を形にします。

経験豊富な専門コンサルタントが現場に入り込み、オープンイノベーションやパートナー開拓の実務をハンズオンで支援。理論と実践を橋渡しし、革新的アイデアを確実な成果へと転換します。「考える」だけでなく「行動する」イノベーションを、私たちは推進します。
その際に事前調査で発見したユーザーの問題や課題、ニーズを再確認することも重要です。問いを発散させるためのフレームワークとしてデザインシンキングでは「How Might We」というフレームワークを用いることもあります。
日本語的な感覚で表現してみると
「どうすれば我々は、<誰>の為に、<何>を実現できるのだろうか?」
というフレームワークです。
「どうしたら我々は入社を希望しているインターン生の為に、実践的かつ、会社の風土を体感してもらえるようなトレーニングを提供できるだろうか」
このような問いの形をより具現化し、たくさんアイディアを出すためにHow Might Weは有効です。
他にも上司や同僚に気を使わないでできる、ブレインストーミングの手法や、思わぬアイディアを創出できるオズボーンのチェックリストなど、多くのアイディア出しのフレームワークもありますので、いろいろご紹介していきたいと思います。
多様なアイディア創出手法の組み合わせ
問いが定まったら、アイディア創出のフェーズに移ります。効果的なアイディア発想のためには、複数の手法を組み合わせることをおすすめします:
- ブレインライティング:参加者が個別に考えをメモし、その後共有する手法。上司や同僚に気を使わずに全員の意見を引き出せます。
- オズボーンのチェックリスト:「拡大する」「縮小する」「組み合わせる」など9つの視点からアイディアを発展させる手法。
- SCAMPER法:代替、結合、応用、修正、他用途、削除、逆転の7つの思考パターンでアイディアを広げます。
- 強制連想法:異なる分野や概念を強制的に結びつけ、斬新なアイディアを生み出す手法。
まとめ:アイディア創造を成功させるためのポイント
新規事業のアイディア創造を成功させるためには、「思いつき」ではなく「フレームワーク」を活用した体系的なアプローチが不可欠です。ターゲットユーザーを明確にし、具体的な問いを立て、多様なアイディア発想手法を組み合わせることで、実現性と革新性を兼ね備えたビジネスアイディアを創出できるでしょう。
今後も、デザインシンキングや新規事業開発に関するさまざまな手法やケーススタディをご紹介していきますので、ぜひご期待ください。
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
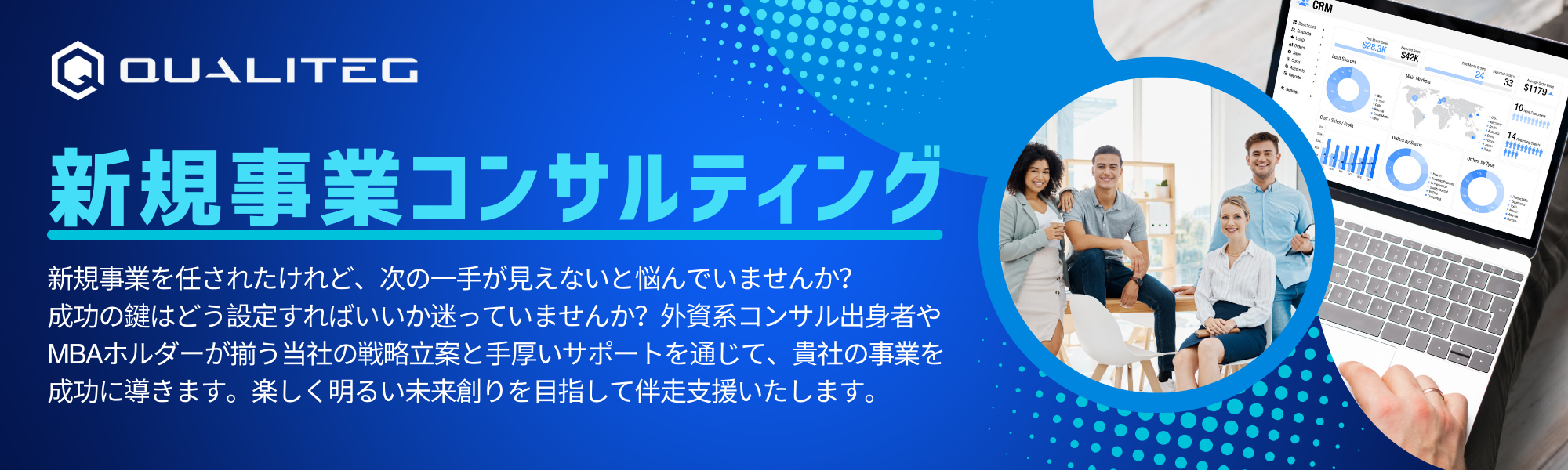
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。次回のコラムも、ぜひご期待くださいね。
navigation





