[AI新規事業創出]Qualitegオリジナル、自社のやるべき新規事業を見極めるためのMVV分析のやり方とは
新規事業の企画では、「なぜ自社で行うべきか」を明確にすることが重要です。多くの企業がこの点を見落とし、役員会でのプレゼンテーションで失敗することがあります。企業のミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)を理解し、それに基づいて新規事業の必要性や目的を定義することで、事業の方向性と一貫性を保ちながら、企業の長期的な目標に寄与する計画が立てられます。
![[AI新規事業創出]Qualitegオリジナル、自社のやるべき新規事業を見極めるためのMVV分析のやり方とは](https://images.unsplash.com/photo-1521316730702-829a8e30dfd0?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDF8fE1pc3Npb258ZW58MHx8fHwxNzEzMDI0MzI5fDA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)
Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
新規事業の企画を検討する上で一番大事なポイントは、その事業をなぜ自社がやるべきなのかをクリアにする必要があります。この問いに答えないでアイディア出しを始めてしまわれるクライアントが多く、そのまま進めてしまうと企画を役員に提案した際に、なぜうちでやる必要があるの?と一蹴されてしまうケースが多いようです。
本日は、なぜ自社でその事業をやる必要があるのかを明確にするための検討方法をお伝えしたいと思います。

MVVとは?
MVVとは「Mission(ミッション)」、「Vision(ビジョン)」、「Value(バリュー)」をまとめて略した言い方で、経営学者のピーター・ドラッカー氏が提唱した企業の経営方針のことです。
企業の存在意義や、果たすべき使命、目指すべき方向性や従業員の行動指針を言語化したもので、これらを定義することで、会社の目指したい道が明確になったり、社員の行動時のよりどころとなり、行動に一貫性がでる、会社のメッセージを周囲に伝えやすい、同じ想いの人が会社に集まってくるなどのメリットがあるため、各社で設定しているものです。
普段の会社生活ではMVVを直接意識して行動する機会が少ないかもしれませんが、会社の方向性が明示されているこのMVVを活用して新規事業のテーマを検討しましょう。
会社によって、MVVすべてを書いていない場合がありますが、その場合はミッションを確認して分析してみましょう。
革新的な企業は、業界の常識や自社のビジネスモデルを絶えず再定義しています。株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、企業のビジネスを共創によって再定義するプログラム。現状分析を通じて固定観念や前提を明らかにし、それらを創造的に問い直す機会を創出します。

アイデアワークショップで「当たり前」を疑う文化を醸成し、オープンイノベーションやパートナー開拓で「自社だけでは思いつかない」異質な視点を取り込むことで、ビジネスの再定義を促進。最先端AI技術の活用支援も含め、経験豊富な専門コンサルタントが、従来の枠組みを超えた新たな価値創造の可能性を開拓します。常識を疑い、枠を超え、未知の領域へ—革新への旅は、再定義から始まります。
有名企業のMVV事例
まず初めに有名企業のミッション、ビジョン、バリューを見てみましょう。
【Mission】世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること
【Vision】ワンクリックで世界の情報へのアクセスを提供すること
Amazon
【Mission】地球上で最もお客様を大切にする企業になること
【Mission】Bring the world closer together.
コミュニティづくりを応援し、人と人がより身近になる世界を実現します。
世界を牽引する企業の共通点として各社の大事にしている概念やこだわり」がミッションに表れていると思います。

こちらのコラムでは仮に設定してみた電気自転車スタートアップ企業のミッションをおいてみて、MVV分析をしてみましょう。
電気自転車スタートアップA社
【Mission】革新的で環境に優しい電動自転車を提供することにより、都市の移動を革命的に改善し、環境持続可能性を促進し、都市生活の質を向上させ、最高のサイクリング体験を提供します。
Step1:Missionの分析・読み解き・用語理解
まず初めに、企業のミッションステートメントを丁寧に読み解き、そこに含まれるキーワードやフレーズの意味を把握します。この段階で、文言の背後にある意図や、企業がどのような価値を提供しようとしているかを理解することが重要です。不明な用語や専門用語があれば、その意味を調べておきましょう。
- 革新的=他社はやってない自社でのオリジナル技術を採用していること
- 環境に優しい=排出ガスゼロで地球温暖化を抑制していること
- 都市の移動を革命的に改善=スマート交通システムを導入すること
- 環境持続可能性を促進=再生可能エネルギーの利用を拡大すること
- 都市生活の質を向上=公共空間の整備と緑化を推進させること
- 最高のサイクリング体験を提供=安全で広い自転車専用道を整備すること
上記のように読み解いた場合、ミッションをまとめると、以下になります。
他社はまだ実施していない自社のオリジナル技術を採用しながら、電気自転車を開発し、排出ガスゼロで地球温暖化を抑制し、合わせてスマート交通システムを導入する。
その際に、再生可能エネルギーの利用を拡大させながら、公共空間の整備と緑化を推進し、安全で広い自転車専用道を整備しつつ、自社の電気自転車を展開していく。

Step2: Missionのコンテキスト理解と具体例の検討
Step2として、企業の歴史、文化、および業界内での立ち位置を調査し、ミッションがどのように形成されたかを理解します。さらに、そのミッションが実際の業務でどのように反映されているかを見るために、具体的な事例(プロジェクト、製品、社会貢献活動など)を調べます。これにより、理論だけでなく実践の面からもミッションの影響を捉えることができます。
もともと電気を活用した製品開発に強みを持っている当社は、地球温暖化防止のために、国土交通省のプロジェクトに参画しながら、自動車道路での電気自転車専用道路の整備と運用の提案を実施している。
Step3: Missionの適用性と影響分析
最後に、ミッションが現在の企業戦略や市場条件に適合しているかを評価します。これには、ミッションの持続可能性、影響力、およびそれが社員や顧客にどのように受け入れられているかを考慮に入れることが含まれます。
世界のトレンドとして、持続可能な社会の実現を目指している中で、当社は電気自転車単体での事業拡大ではなく、安全な自転車専用道の整備やスマート交通システムの導入を目指しながら、事業展開を行っていく。これらは都市部の渋滞時の通勤問題解決の一助となり、都市部で働く人々に評価されている。
新規事業検討の方向性とは
ここまで分析してみると、この企業の強みは、電気自転車の運用で利用可能なオリジナルの技術を保有している点、都市部に暮らす人々に評価されている点、が明らかになります。
そのため、新たな事業の柱を考えることを目的として、新規事業のアイディアを検討する際には、エコフレンドリーな自社のブランディングを活用して、都市部で働く人にアプローチできるものを考えていく、という方針が見えてきます。
このようなステップで企業のMVVを分析し、次の一手である新規事業のアイディアを検討していきましょう。
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
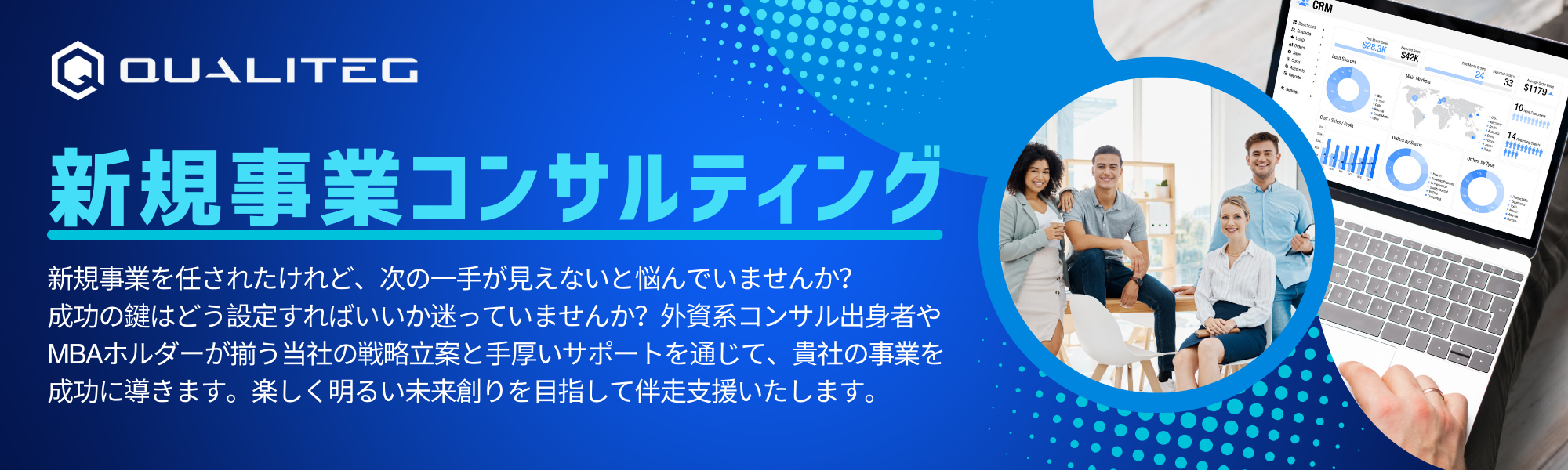
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。次回のコラムも、ぜひご期待くださいね。
navigation





