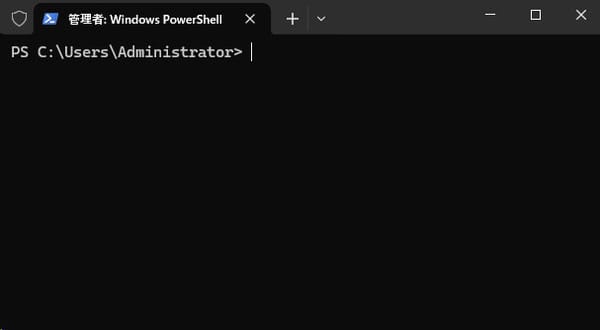NumPy/PyTorch
GPUサービスで「Segmentation Fault 」に出会ったら~分析から解決までの実践アプローチ~
こんにちは! 今日は仮想環境+GPUなサービスにおける「Segmentation Fault」について、分析と対処法について書いてみたいと思います。 Segmentation Faultの本質と特徴 Segmentation Faultは、プログラムが保護されたメモリ領域にアクセスしようとした際にOSが発生させる例外です。 今回は複数のGPUサービス(つまりGPUを使うプロセス)が動作していて、そのうちの1つを再起動したときに発生しました。 毎回発生するわけではありません。むしろ数百回の起動に1回程度ですが、1回でも発生すると絶望的な結果につながります。というのも、1つのGPUサービスの停止が SPOF となってサービス全体に影響が発生します。かつ、1回でも「Segmentation Fault」が発生してしまうと、その原因となったプロセスが二度と起動しなくなる、というやっかいな現象でした。 このように「普段は正常に動作しているのに突然動かなくなる」というのがデバッグを非常に難しくします。 とくにGPU+仮想化の組み合わせで従来のC++アプリよりも発生確率がぐっとあがる印象








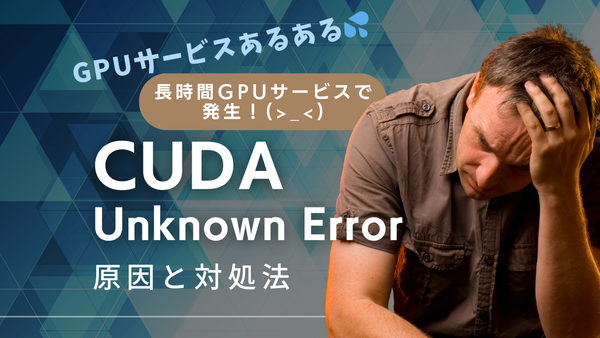
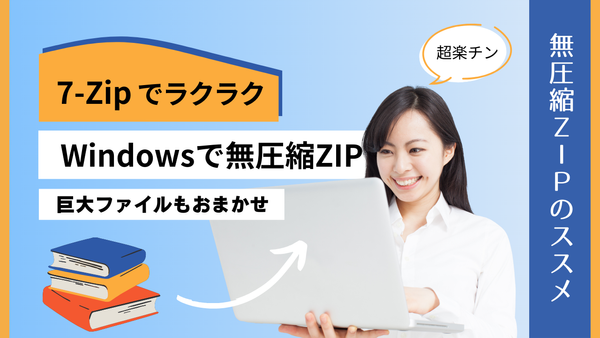

![[vLLM] To use CUDA with multiprocessing, you must use the 'spawn' start method の対処法](https://images.unsplash.com/photo-1597872200969-2b65d56bd16b?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDh8fGdwdXxlbnwwfHx8fDE3MzkyMzYxNTh8MA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=600)