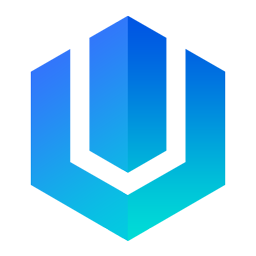推論時torch.tensor(sourceTensor)ではなくて、sourceTensor.clone().detach()を使おう

PyTorchのテンソル操作最適化: 警告メッセージの理解と解決
こんにちは!
Qualiteg プロダクト開発部です。
PyTorch 1.13にて、次のような警告メッセージに遭遇しました
UserWarning: To copy construct from a tensor, it is recommended to use sourceTensor.clone().detach() or sourceTensor.clone().detach().requires_grad_(True), rather than torch.tensor(sourceTensor).
この記事では、この警告の意味を解説し、修正方針についてかきたいとおもいます。
torch.tensor() よりも .clone().detach() のほうがおすすめなのか
それは、PyTorchがテンソルと自動微分(オートグラッド)をどのように扱うかに関係があります。
torch.tensor() をつかうと「勾配計算=自動微分どうするねん」っていう意思表示がハッキリしないんです。
一方clone().detach()は「勾配配計算しないよ」をあらわし、clone().detach().requires_grad_(True)は「勾配計算有効」をあらわすので、コードから意図がよみとれる&明示的に指定できる、のがポイントです。
clone().detach()では、元のテンソルとメモリを共有せず、計算グラフから切り離された新しいテンソルが作成されます。これにより、特に勾配や誤差逆伝播を扱う際に、予期せぬ動作を防ぐことができるというわけです。
推論で使うときはどう書けばいい?
結論からいうと、推論時には sourceTensor.clone().detach() をつかいましょう。
その理由は以下のとおりです
- 計算効率:
推論時には通常、勾配計算は不要です。detach()を使うことで、テンソルを計算グラフから切り離し、不要な勾配計算を防ぎます。これにより、メモリ使用量が減少し、計算速度が向上します。 - メモリ管理
clone()は新しいメモリ領域にデータをコピーします。これにより、元のテンソルに影響を与えることなく、安全に操作を行えます。 - 意図しない変更の防止
detach()を使用することで、誤って勾配計算を行ってしまうリスクを減らせます。これは特に大規模なモデルや複雑なアーキテクチャで重要です。 - モデルの固定
推論時には当然モデルのパラメータを更新したくないのでdetach()を使うことで、誤ってモデルが更新されることを防げます。
チェインしてるメソッドの詳細説明
clone()メソッド:- 新しいテンソルを作成し、元のテンソルのデータをコピーします。
- これにより、元のデータに影響を与えることなく安全に操作できます。
detach()メソッド:- テンソルを現在の計算グラフから切り離します。
- 勾配計算が不要な場合(例:推論時)に特に有用です。
まとめ
- sourceTensor.tensor() でコピーするのはコンテクストがあいまいなので使わないようにしましょう。
- 推論時は
clone().detach()を使用します。勾配計算が不要なため、メモリ使用量を減らし、計算速度を向上させます。 - 学習時は 勾配計算が必要な場合は、
clone().detach().requires_grad_(True)を使用します。これにより、新しいテンソルで勾配計算が可能になります。