[AI新規事業創出]Qualitegオリジナル、事業責任者との合意形成のための新規事業方向性まとめ方
このブログでは、新規事業の事業責任者とのゴール合意形成方法を解説しています。Step1では事業のビジョンと目標を明確化し、数値目標を設定します。Step2では達成のためのロードマップとKPIを作成し、Step3では定期的なミーティングで進捗を共有し調整します。これにより、新規事業推進の体制を効果的に整えることができます。
![[AI新規事業創出]Qualitegオリジナル、事業責任者との合意形成のための新規事業方向性まとめ方](https://images.unsplash.com/photo-1576670659221-578949ce6284?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDMyfHxEaXJlY3Rpb258ZW58MHx8fHwxNzEzMDI1MDU2fDA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)
Qualiteg blogを訪問してくださった皆様、こんにちは。Micheleです。AIを活用した新規事業やマーケティングを手がけている私には、クライアントからよく寄せられる質問があります。AIを用いた事業展開を検討されている方々が共通して直面するであろう課題に対して、このブログを通じて私なりの解答をご提供したいと思います。
このブログでは事業責任者と新規事業で達成すべきゴールをどのように事前に合意形成すべきかについて解説していきます。
Step1: ゴールの明確化と認識の共有
まず、初めに事業のビジョンと目標を明確に定義し、それを文書化します。パワーポイントなどでエグゼクティブサマリーとして1ページにまとめ、事業責任者と一緒に具体的な数値目標(売上、顧客数、市場シェアなど)について、それぞれのゴールが事業の成功にどのように寄与するかを議論します。
このフェーズでのポイントは目標がいかにリアリスティックで達成可能かどうかが評価されますので、自分でも達成できないような例えば1年で売上100億円達成のような大きすぎる目標は避けるようにしましょう。
初めに行ったMVV分析をもとに、自社がなぜその新規事業を行うべきか、自社のMVVの振り返りと読み解き、コンテキスト理解も踏まえたうえで新規事業を実施する必要性について説明いします。
次に説明するのは、何をもって新規事業の事業化判断を行うかの基準について議論します。前コラムで解説した定量的目標設定の内容を明確化し、具体的な数値をもって、この数値を達成するために新規事業を行うという趣旨をお伝えしましょう。
多くの企業では、イノベーションが理念としては語られても、実際の行動に結びつかないことがあります。株式会社Qualitegの Innovation-Crossは、この「言行一致のギャップ」を埋める共創支援プログラム。企業の現状と課題を徹底分析し、具体的なアクションへと落とし込む戦略を策定します。アイデアワークショップやハッカソン企画を通じて実践的な場を創出し、「自社だけでは変わりにくい」イノベーション行動を促進。

オープンイノベーションやパートナー開拓の実践を通じて、外部との協業による価値創造の体験を積み重ねます。経験豊富な専門コンサルタントが伴走し、理念から行動へ、行動から成果へという変革の流れを確実に実現。イノベーションを「語る文化」から「行動する文化」へと変革します。
Step2: ロードマップの作成
続いて必要なことは、ロードマップの作製になります。合意されたゴールを達成するための、開発スケジュール、マーケティング戦略立案などの主要なマイルストーンを設定しましょう。
それらのマイルストーンの達成判断をするための数値目標としてのKPI(重要業績評価指標)を設定することで、手戻りがない事業開発を行うことが可能です。

Step3: コミュニケーションと調整
最後に必要なことはコミュニケーション計画の説明です。事業責任者との定期的なミーティングを設けて、進捗状況を共有して計画の進捗度合いを報告します。
事前にコミュニケーション計画を設定することで、すべての関係者が同じ情報を持ち、例えば競合から類似サービスのリリース情報が出た場合などの、万が一変更が必要になった場合にも備えることが可能ですので、チームで共同して対応できる新規事業推進体制を作ることが可能です。
事業責任者にあらゆる観点で事前にコミットすることは、担当者にとってはハードルが高いケースもありますが、事前にコミュニケーション計画やマイルストーンを提示することで信頼感も生まれ、新規事業を推進する上で役に立つことでしょう。
コラムを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私たちQualitegは、AI技術や新規事業の企画方法に関する研修およびコンサルティングを提供しております。もしご興味をお持ちいただけた場合、また具体的なご要望がございましたら、どうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。
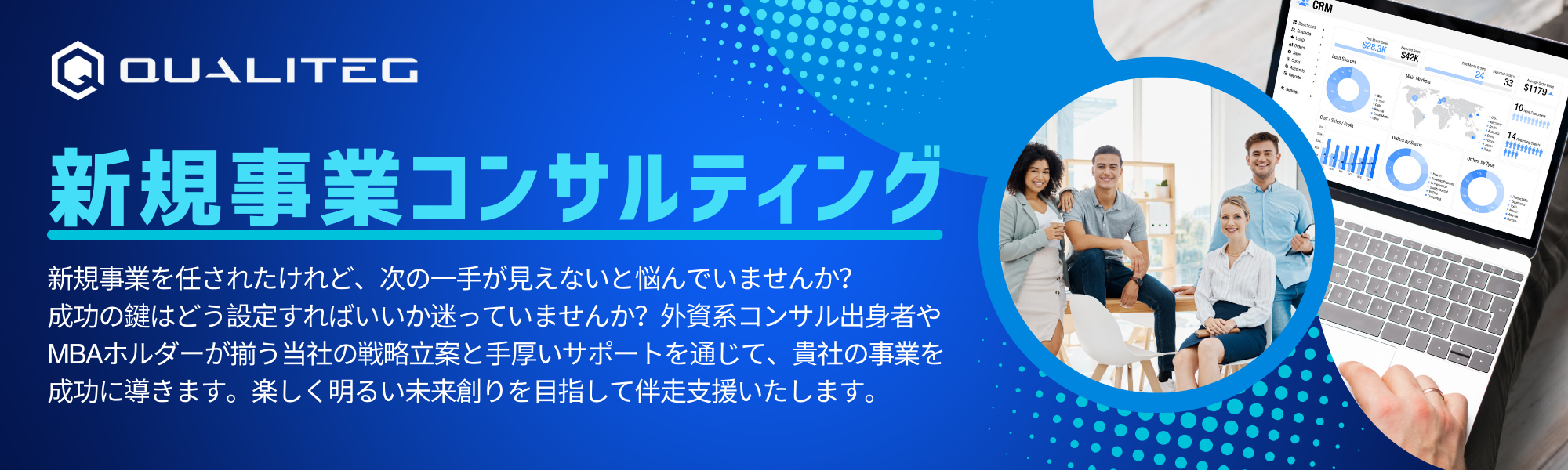
また、新規事業創出のステップを体得したいという方にご好評のワークショップも実施しております。それぞれの担当者の方が役員目線で事業を考えるという点にフォーカスしたトレーニング内容となっており、企画担当者の方だけではなく、カウンターパートのエンジニア、デザイナー、マーケターの方にもご受講いただけるコンテンツとなっております。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。次回のコラムも、ぜひご期待くださいね。
navigation





