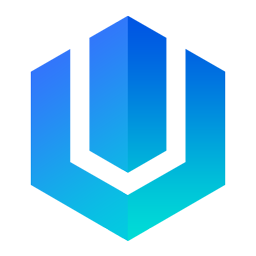発話音声からリアルなリップシンクを生成する技術 第5回(後編):Transformerの実装と実践的な技術選択
なぜGPTで成功したTransformerが、リップシンクでは簡単に使えないのか?データ量・計算量・過学習という3つの課題を深掘りし、LSTMとTransformerの実践的な使い分け方を解説。さらに転移学習という第三の選択肢まで、CEATEC 2025で見せた「アバター」の舞台裏を、クオ先生とマナブ君の対話でわかりやすく紐解きます。

こんにちは!
CEATEC 2025への出展も無事に終了し、怒涛の4日間から早くも数週間が経ちました。
幕張メッセは相変わらずの熱気でしたが、気がつけばすっかり秋も深まり、朝晩はめっきり涼しくなりましたね。
たくさんの来場者の方々からいただいた貴重なフィードバックを整理しながら、改めて技術の奥深さを実感しています。展示会場では、キャラクターが自然に話す姿をご覧いただき、「本当に音声に合わせて動いているの?」「どうしてこんなに自然なの?」といった嬉しい驚きの声を多数いただきました。
本シリーズはその技術面での舞台裏の物語となります。
さて、前編では、Transformerの革新的なMulti-Head Self-Attention機構の仕組みを詳しく見てきました。8つの専門家が異なる観点から音素間の関係を分析し、Query、Key、Valueの巧妙な役割分担により、全ての音素が同時に相互作用できる画期的な仕組みを理解しました。理論的には、これでLSTMの長距離依存問題は完全に解決されたかのように見えます。
しかし、実際にTransformerをリップシンクタスクに適用しようとすると、思わぬ壁にぶつかります。なぜGPTやBERTのような大規模言語モデルで成功したTransformerが、リップシンクでは簡単に導入できないのでしょうか。
今回の後編では、まずFeed-Forward層の役割を説明し、LSTMとTransformerの構造的な違いを明確にします。そして、Transformerが抱える3つの重大な課題を掘り下げていきます。桁違いに少ないサンプルで学習できるLSTMに対し、なぜTransformerは膨大なサンプルを必要とするのか。入力が長くなると計算量が爆発的に増加するO(n²)問題はどれほど深刻なのか。そして、自由度の高さゆえに陥りやすい過学習の罠とは何か。
これらの課題を理解した上で、現実的な解決策としてのハイブリッドアプローチを紹介します。LSTMの効率性とTransformerの表現力、両者の長所を組み合わせることで、限られたリソースでも高品質なリップシンクを実現する方法を探ります。さらに、感情表現への拡張という次なる挑戦についても触れ、実際の製品開発における技術選択の具体的な指針を提示していきます。
理想と現実のギャップを埋める、実践的な知見を一緒に学んでいきましょう。
「発話音声からリアルなリップシンクを生成する技術」
バックナンバー
- 第1回:音素とwav2vec
- 第2回:AIを使ったドリフト補正
- 第3回:wav2vec特徴量から口形パラメータへの学習
- 第4回:LSTMの学習と限界、そしてTransformerへ
- 第5回(前編):Transformerの実装と実践的な技術選択
第5回 後編
1.2 Feed-Forward層:特徴変換
さて、なんといきなり1.2節から唐突にはじまってしまいましたが、前回からの続きとなりますので、ご了承ください^^;
Self-Attention層の後には、Feed-Forward Network(FFN)が続きます。これは、各位置に対して同じ変換を適用する2層の全結合ネットワークです。512次元から2048次元に拡張し、ReLU活性化関数を適用した後、再び512次元に圧縮します。
この層の役割は、Self-Attentionで得られた文脈情報を、より表現力の高い空間で変換することです。拡張と圧縮のプロセスにより、複雑な非線形変換を学習できます。
1.3 LSTMアーキテクチャとの構造的な違い
TransformerとLSTMの最も本質的な違いは、情報の流れ方にあります。LSTMでは情報が一方向(または双方向)に順次流れるのに対し、Transformerではすべての位置が相互に直接接続されています。
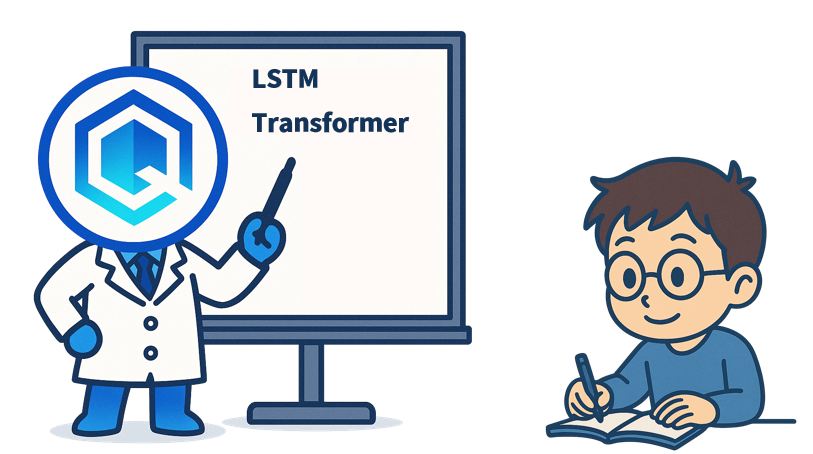
構造的な違いは、学習の性質にも影響します。LSTMは「時系列は順番に処理すべき」という強い帰納バイアスを持つため、少ないデータでも学習しやすい傾向があります。一方、Transformerは制約が少ない分、より柔軟な学習が可能ですが、その分多くのデータを必要とします。
また、Transformerは層を深く積み重ねやすいという利点もあります。各層で全体を見渡せるため、深い層でもグローバルな情報を保持できます。これにより、より複雑な音素間の関係を学習することが可能になります。
2. Transformerの落とし穴:自由度の高さゆえの課題
2.1 なぜ大量のデータが必要なのか
Transformerの最大の課題は、その柔軟性の高さゆえに、膨大な量の学習データを必要とすることです。Transformerがデータを大量に必要とする根本的な理由は、その柔軟性の高さにあります。
LSTMは「時系列データは順番に処理する」という強い仮定(帰納バイアス)を持っています。これは、モデルが最初から「正しい方向」を向いているようなものです。一方、Transformerにはこのような仮定がほとんどありません。どの位置とどの位置を関連付けるべきかを、すべてデータから学習する必要があります。
2.2 計算量の爆発的増加(O(n²)問題)
Transformerのもう一つの大きな課題は、計算量が入力長の2乗に比例して増加することです。これは、すべての位置ペアの関係を計算するという、Self-Attentionの本質的な性質に起因します。
例えば、50音素の文章を処理する場合、LSTMでは50回の順次計算で済みますが、Transformerでは50×50=2500回のAttention計算が必要になります。100音素なら10000回、200音素なら40000回と、急激に計算量が増加します。
実際のアプリケーションでは、この計算量の問題はメモリ使用量にも直結します。Attention行列を保持するために必要なメモリも入力長の2乗で増加するため、長い音声を処理する際には、分割処理やメモリ効率的な実装が必要になります。
2.3 過学習しやすい理由
また、Transformerの高い表現力は諸刃の剣で、学習データに過度に適合してしまう「過学習」のリスクも高くなります。特に、限られたデータで学習する場合、この問題は深刻です。
過学習が起こると、学習データでは完璧な性能を示すものの、新しいデータに対してはうまく機能しません。例えば、特定の話者の癖を過度に学習してしまい、他の話者では不自然な口の動きを生成してしまうといった問題が発生します。
過学習※を防ぐためには、Dropout、Weight Decay、Early Stoppingなどの正則化技術を適切に使用する必要があります。また、データ拡張も重要で、限られたデータから多様なバリエーションを生成することで、モデルの汎化性能を向上させることができます。
※参考:過学習や汎化性能をはかる指標として平均二乗誤差(MSE)があります。当社メンバーの執筆した以下の記事がわかりやすいのであわせてご参照ください

しかし、根本的な解決策は、やはり十分な量の学習データを用意することです。大規模言語モデルの成功が示すように、Transformerは十分なデータがあれば驚異的な性能を発揮します。問題は、リップシンクタスクにおいて、そのような大規模データセットを構築することが現実的かどうかという点にあります。とくに当社のようなベンチャー・スタートアップにはデータセット構築に必要な許諾を得ながらこうしたデータセットを構築するハードルが高いのも事実です。
これらの課題を踏まえると、Transformerは確かに強力ですが、すべての状況で最適な選択とは限らないことが分かります。
そこで、次章では、LSTMとTransformerの長所を組み合わせた、より実践的なアプローチについて見ていくことにします。
3. 実践的な選択:LSTMとTransformerをどう使い分けるか
3.1 それぞれの強みを理解する
ここまで見てきたように、LSTMとTransformerにはそれぞれ明確な強みと弱みがあります。重要なのは、どちらが優れているかではなく、どの場面でどちらを選ぶべきかを理解することです。
3.2 データ量による選択基準
実際の開発現場では、利用可能なデータ量が最初の判断基準になることが多いです。
少量データの環境では、LSTMが圧倒的に有利になります。
LSTMは「時系列データは順番に処理すべき」という強い帰納バイアスを持っているため、少ないデータでも効率的に基本パターンを学習できます。
これは、あらかじめ正しい方向性が組み込まれているため、少ない試行錯誤で目的地に到達できるようなものです。また、モデルの構造がシンプルなため、過学習のリスクも低く抑えられます。限られたデータで安定した性能を出す必要がある場合、LSTMは信頼できる選択肢となります。
一方、大量のデータが利用可能な環境では、Transformerの真価が発揮されます。十分なデータがあれば、Transformerは音素間の複雑な関係性を学習し、より自然で多様な表現を生成できます。
3.3 リアルタイム性による選択
つぎはリアルタイム性という観点でLSTMとTransformerについて考えてみましょう。
リアルタイム処理が必要な場面では、LSTMの特性が大きな利点となります。LSTMはストリーミング処理に対応しており、音声が入力されるたびに即座に口の形を生成できます。数十ミリ秒という極めて低い遅延を実現できるため、ライブ配信やビデオ会議、リアルタイムアバターなど、即応性が求められる用途に最適です。ユーザーが違和感を感じることなく、自然なインタラクションを実現できます。
対照的に、バッチ処理が可能な場合はTransformerの強みを最大限に活用できます。事前に収録された音声を処理する動画制作やアニメーション制作では、処理時間よりも品質を優先できます。Transformerは音声全体を俯瞰して処理するため、前後の文脈を完全に考慮した、より自然で表現豊かなリップシンクを生成できます。事前レンダリングが可能な環境では、この品質の差が最終的な作品のクオリティを大きく左右することになります。

3.4 計算リソースとコストの観点
開発・運用コストも、技術選択において無視できない重要な判断基準です。
リソースが限られている環境では、LSTMが現実的な選択となることが多いです。学習時間は通常数時間から1日程度で完了し、モデルサイズも比較的コンパクトです。ただし、LSTMには重要な制約があります。その逐次処理という性質上、GPUでのバッチ処理による並列化が困難なのです。複数の音声を同時に処理しようとしても、各タイムステップを順番に処理する必要があるため、GPUの並列計算能力を十分に活かせません。
たとえばH100のような最新のエンタープライズ向けGPUには、MIG(Multi-Instance GPU)という技術があり、一つの物理GPUを最大7つの独立したGPUインスタンスとして扱うことができます。
これにより、複数のLSTMモデルを並列っぽく動かすことは可能です。また、推論サーバーを工夫することで、複数のリクエストを効率的に処理することもできます。しかし、このようなアプローチはとても複雑で、各インスタンスのリソース配分を管理し、リクエストを適切にルーティングし、メモリを効率的に使用するための仕組みが必要になります。
さらに、LSTMの場合、各インスタンスが処理できるのは結局一つのストリームだけなので、Transformerのような真の並列バッチ処理と比較すると、GPUの計算能力を完全に活用しているとは言い難い面があります。またH100のようなGPUがバンバン購入できる体力があるなら、大量データ、大量学習のTransformerを使って工夫するほうがいいんじゃない?という気もします。
で、そのTransformerのほうですが、3.3の繰り返しにはなりますが、Transformerは設計段階から並列処理を前提としているため、単一のモデルインスタンスで複数の入力を効率的にバッチ処理できます。Self-Attention機構は、バッチ内のすべてのサンプルを同時に処理できるため、GPUのテンソルコアを最大限に活用できます。特に大規模なバッチサイズでの処理において、その効率の差は顕著に現れます。
3.5 実践的な判断
とはいえ、実践的な判断としてLSTMかTransformerか、どのように選べばよいでしょうか。
【データ量】
まず最初に確認すべきなのは、利用可能なデータ量(データセットの大きさ)です。ただし、前述のとおり十分なデータがない場合、どんなに他の条件が整っていても、Transformerで良い結果をだすのは困難です。
【リアルタイム性】
次にリアルタイム性の要件を検討します。ミリ秒単位の遅延が許されない場面では、LSTMが唯一の現実的な選択肢となるでしょう。(LSTMが並行性が苦手な例を前述しましたが、たとえば、特定の用途、たとえばテーマパークや施設等での案内をする案内アバターなど、並行性があまり求めらないが、リアルタイム応答してほしいときなどは有用で実際、こうしたところでLSTMベースのモデルが活躍している例もあります)
【計算リソース】
続いて、計算リソースの制約を考慮します。GPUを常時使用できない環境や、運用コストに厳しい制限がある場合は、LSTMを選択することが賢明です。
【開発期間や予算】
最後に、プロジェクトの目標と開発期間を総合的に判断します。最高品質を追求し、十分な開発期間がある場合のみ、Transformerの採用を検討すべきでしょう。
3.6 将来を見据えた選択

多くの成功事例では、段階的な進化パスを辿っています。最初はLSTMで実用最小限の製品を開発し、市場に投入します。
その後、ユーザーフィードバックを収集しながらデータを蓄積し、サービスの成長とともに技術基盤を強化します。必要に応じてTransformerへの移行や、両者をうまく組み合わせたハイブリッドアプローチの採用を検討することで、リスクを最小限に抑えながら、段階的に品質を向上させることが可能です。
このような柔軟なアプローチにより、技術的な理想と現実的な制約のバランスを取りながら、持続可能な開発を進めることができます。
3.7 第三の選択肢:転移学習という突破口
さて、ここまでLSTMとTransformerのトレードオフについて見てきましたが、
実はもう一つ重要な選択肢があります。
それが転移学習です。

転移学習では、大規模な事前学習済みモデルが持つ知識をそのまま活用できます。
音声認識の分野では、何百万時間もの音声データで学習されたモデルが存在します。これらのモデルは、音素の識別、話者の特徴、イントネーションパターンなど、音声に関する深い理解を既に持っています。この知識をリップシンクに転用することで、少ないデータでも高品質な結果を得ることができるのです。
特に素晴らしいことに、商用利用可能なオープンソースのベースモデルが豊富に存在します。最先端の音声認識モデルが、制約の少ないライセンスで公開されています。これらのモデルは、研究機関や大企業が莫大なコストをかけて開発したものですが、誰でも利用できます。これらの研究成果を基盤として活用できるのは大変ありがたいです。
音素と口形状の対応関係を学習するためには、確かに(口形の)モーションキャプチャデータが必要になります。
しかし、ここでも転移学習の恩恵は大きく、必要なデータ量は劇的に削減されます。ゼロから学習する場合と比較すると、桁違いに少ないデータで実用的な性能を達成できるのです。もちろんこれまで解説してきたあらゆる技を使います。モーションキャプチャ技術の進歩も、この取り組みを後押ししています。最新のシステムでは、短時間で高精度な口の動きを記録できるようになりました。以前は口元にマーカーをつけて計測していたものが、最近ではマーカーレスで処理できるようになっています。
また、基本的な音素セットをカバーするデータ収集は、適切な計画があれば非常に効率的に行えます。プロの声優さんやナレーターさんと協力することで、質の高いデータを短期間で収集することが可能です。もちろん、データセット構築にあたり、そうした協力者の皆様と契約、必要な許諾を得る必要がありますが、数万人規模を数百人規模まで減らすことが可能ですので、ベンチャースタートアップにとっても、より現実的な範囲でこうした取り組みを進めることができます。
さらに、データ拡張技術を活用することで、限られた収録データから多様なバリエーションを生成できます。話速の変化、声の高さの調整、環境ノイズの追加など、様々な手法を組み合わせることで、実質的なデータ量を大幅に増やすことができます。これは、少ない材料から多彩な料理を作り出す、創造的な料理人の技のようなものです。
転移学習を活用することで、LSTMの効率性とTransformerの表現力という二者択一から解放されます。少ないデータでもTransformerベースの強力なモデルを使うことができ、かつ実装も比較的シンプルです。多くの場合、既存のフレームワークやライブラリを使って、数行のコードで転移学習を実装できます。
ただし、転移学習は万能薬ではありません。ベースモデルと目的タスクの相性、fine-tuningの方法、データの質など、考慮すべき要素は多くあります。それこそがいわゆる「秘伝のタレ」なのですが、これらを適切に活用すれば、限られたリソースでも競争力のあるリップシンクシステムを構築できる、強力な武器とすることが可能です。
このように、転移学習は「データが少ないからLSTM」「データが豊富だからTransformer」という単純な二元論を超えた、現実的で柔軟な第三の選択肢となります。

4. まとめと次回予告
今回のまとめ:理論から実践へ
本記事では、前編でTransformerの具体的なネットワーク設計から始まり、その実装上の課題、そして後編でLSTMとTransformerの実践的な使い分けについて詳しく解説しました。
Transformerの革新的なSelf-Attention機構により、長距離依存の問題は理論的には解決可能になりました。しかし、その代償として大量のデータと計算リソースが必要になることも明らかになりました。実際の製品開発では、これらのトレードオフを慎重に考慮する必要があります。
さらに、転移学習という第三の選択肢も紹介しました。商用利用可能なオープンソースモデルを活用することで、少ないデータでもTransformerベースの強力なモデルを構築できます。音声認識で培われた知識を転用し、最小限のモーションキャプチャデータで実用的なリップシンクシステムを実現する道が開かれています。
実際のプロダクト開発では、段階的なアプローチが有効で、まずLSTMで素早くプロトタイプを作り、市場の反応を見ながらデータを蓄積し、必要に応じてTransformerや転移学習への移行を検討する。このような柔軟な戦略により、技術的な理想と現実的な制約のバランスを取りながらプロダクトを成長させていく、ということになるとおもいます
次回予告:見過ごされがちな「最後の瞬間」の課題
次回は、この音声終端での不自然な挙動がなぜ発生するのか、その技術的メカニズムを詳しく解説します。モデルの不確実性、学習データの曖昧性、離散化による情報損失など、AI技術の根本的な課題が、この小さな「終わりの瞬間」に凝縮されています。
そして、この問題に対する実践的な解決策についても紹介します。シンプルな後処理から、最新のAI技術を使った根本的なアプローチまで、様々な手法を比較検討していきます。
理論を学んだ今、実際の製品開発で直面する「リアルな課題」とその解決法を一緒に探求していきましょう。小さな問題に見えるかもしれませんが、その解決への取り組みが、より自然で説得力のあるバーチャルキャラクターの実現につながります。
それでは、次回もお楽しみに!