AIエージェント時代の新たな番人「ガーディアンエージェント」とは?

こんにちは!今日は先日ガートナーが発表したガーディアンエージェントについて解説します
ガートナーの公式定義
ハイプカーブで有名なガートナーは2025年6月に、ガーディアンエージェントに関する見解を発表しました。ガーディアン・エージェントとは、AIとの安全で信頼できるやりとりを支援するために設計されたAIベースのテクノロジです。
ざっくりいうと、
「AIエージェントが来るよ」と予言したガートナー社は、次は、「ガーディアンエージェントが来るよ」と予言しました。なぜガーディアンエージェントが来るのでしょうか?本稿では、そのあたりを考察していきたいと思います。
なぜ今、AIの「監視役」が必要なのか
2025年、私たちは本格的なAIエージェント時代の入り口に立っています。AIが単なるツールから、自律的に判断し行動する「エージェント」へと進化する中で、新たな課題が浮上しています。
従来のAIとエージェント型AIの違い
さて、ガーディアンエージェントが必要になる理由として、生成AI(以後AIと呼びます)の急速な進化があげられます。従来のAIとエージェント型AIの違いを思い出してみましょう。
このように、エージェント型AIは「指示待ち」ではなく「自律的(自ら考えて)に行動」するので、従来のAIにくらべ圧倒的に強力になります。
エージェント型AI強力すぎて怖くないですか?
➡だからこそ『ガーディアンエージェント』が必要
エージェント型AIは強力な分、リスクも大きい
- 誤った判断で大きな損害を与える可能性
- 権限を超えた行動を取るリスク
- 予期しない連鎖反応を引き起こす危険性
これらのリスクを管理するために、
ガーディアンエージェントが「AIの監視役」として必要
ということで、このようなリスクに対処するためガートナーは「ガーディアンエージェント」という概念を提唱したのでしょう。
ガーディアンエージェントの本質:AIを守るAI
このように人間が24時間365日AIの動作を監視することが現実的でなくなる中、AIがAIを監視するというアプローチは必然の流れでしょう。
この技術は、単なる監視ツールではなく、必要に応じて積極的に介入し、問題のある動作を修正または停止できる点にあります。まさに、デジタル世界における自動化された「守護者(ガーディアン)」と言えます。
3つの主要カテゴリー
ガーディアンエージェントは、その機能によって3つのタイプに分類されます
1. レビュアー
AI生成したコンテンツや出力を精査し、その精度や適切性を評価します。例えば、チャットボットの回答が正確で、企業ポリシーに準拠しているかをチェック・レビューする役割を担います。
2. モニター
システムの動作を継続的に観察し、異常なパターンや潜在的な問題を検出します。これは、セキュリティカメラのように常に監視し、必要に応じてアラートを発し人間やAIに追加の対応を促す機能です。
3. プロテクター
最も積極的な介入を行うタイプで、問題のある動作を検出した際に、即座に修正措置を取ったり、動作を停止させたりします。いわば、AIシステムの緊急ブレーキとして機能します。
2025年の技術トレンドにおける位置づけ
エージェント型AIとの密接な関係
繰り返しになりますが、
ガートナーが発表した「2025年の戦略的テクノロジートレンド」では、エージェント型AIが最重要項目として挙げられています。
今回、ガーディアンエージェントは、このエージェント型AIを安全に展開するための不可欠な要素として位置づけられています。
エージェント型AIが人間に代わって複雑なタスクを自律的に実行するようになると、その動作の正確性と安全性を確保することが極めて重要にになることは前述のとおりです。
ここで、同じくガートナー社が2023年のトレンドとして発表した「TRiSM」という概念についても考えてみましょう。
AI TRiSMフレームワークの実装
AI TRiSMとはAIの信頼性(トラスト)、リスク、セキュリティマネジメントのことで、「AIを安全に・信頼できる形で使うための管理フレームワーク」です。
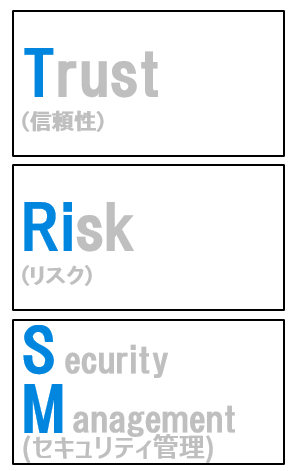
わかりやすく言うと...
従来:「AIすごい!どんどん使おう!」
↓
問題:「あれ?このAI、嘘ついてる」「勝手に変なことしてる」「個人情報漏れてる」
↓
解決:AI TRiSM「AIを使う前に、ちゃんと管理体制を作ろう」AI TRiSM とガーディアンエージェントの関係
まずAI TRiSM とガーディアンエージェントの関係を整理しましょう。
AI TRiSM は 「何を管理すべきか」のフレームワーク
AI TRiSM = 「何を管理すべきか」のフレームワーク
├── Trust➡信頼性を管理
├── Risk➡リスクを管理
└── Security Management ➡セキュリティを管理(統合的に)
ガーディアンエージェントはそれを「どう自動化するか」の実装
ガーディアンエージェント = 「どう自動化するか」の実装
├── レビューアー(検証を自動化)
├── モニター(監視の自動化)
└── プロテクター(緊急ブレーキを自動で踏む、制御を自動化)
ここを抑えたうえで、では、いままでと今後はどうなるのかを、わかりやすくいうと、
いままではAI TRiSM は人間が手動でやっていたのにたいして、これからは、ガーディアンエージェントにより自動化される
ことになるでしょう。AIによる自動監視・対応により人間によるオペレーションではとても追いつかず、対応漏れが発生するという事態を回避することができます。
では次に、日本のAI活用シーンにおいて実際のところはどうなるかを考えてみましょう。
AI TriSM の体制構築、準備は必ず必要になる
実際のところ、2025年の日本においては、今この瞬間は先進的企業において AI TriSM が認知され、体制準備がはじまったところではないでしょうか。
とはいえ、「ガーディアンエージェント」が現在の額面通りの定義で本当に流行るかどうかはおいておいてもAIエージェントの急激な進化と、それにたいするネガティブな影響を最小限に押させるための策として自動化されたAI TRiSM が必要になるのはほぼ確実です。
いまからでも全く遅くはありませんので、AI TRiSM を下敷きにしAIセキュリティ体制構築計画の策定をはじめましょう。
さて、そうした計画の指針決めに役立ちそうな未来展望(ガートナーによる)についても触れておきます。
未来展望:2030年に向けて
市場予測
ガートナーの予測によると、2030年までにガーディアンエージェント技術は、急成長するエージェント型AI市場の10-15%を占めることになります。これは、数千億円規模の市場機会を意味しています。
技術の進化
短期的展望(2025-2026年)
- 日常業務の15%がAIエージェントによって自律的に実行される
- エンタープライズソフトウェアの3分の1にエージェント機能が搭載される
中期的展望(2027-2028年)
- AIアプリケーションの70%がマルチエージェントシステムを採用
- ガーディアンエージェントが企業AI導入の標準要件となる
長期的展望(2029-2030年)
- AIエージェントが多くの業務システムで人間を上回る主要ユーザーとなる
- 業界特化型のガーディアンエージェントエコシステムが確立
今すぐ始められる「ガーディアンエージェント」への第一歩
理想と現実のギャップ
ここまでガーディアンエージェントの将来像を見てきましたが、正直なところ、2025年の現在では
- 本格的なAIエージェント:まだ実験段階
- 自動化されたAI TRiSM:コンセプト先行で実装は限定的
- ガーディアンエージェント:製品化はこれから
つまり、理想は素晴らしいけど、今すぐ使える製品はまだないという状況です。
でも、リスクは今そこにある
しかし、AIのリスクは「将来の話」ではありません。今この瞬間も
😱 現在進行形のリスク
├── 社員が機密情報をLLMサービスに入力している
├── AIが生成した不正確な情報を顧客に提供している
└── 個人情報や企業秘密が外部AIサービスに蓄積されている
が発生しているかもしれません。
今できることから始めよう:LLMセキュリティ
ガーディアンエージェントの実現を待つ間にも、企業の機密情報は日々AIシステムを通じて漏洩のリスクにさらされています。
特に深刻なのは、情報の流れが双方向であることです。従業員が機密情報をAIに入力する「アウトバウンドリスク」と、AIが不適切な情報を生成・表示する「インバウンドリスク」、この両方を今すぐ防御する必要があります。
アウトバウンド防御:あなたの秘密がAIに流出する前に
多くの企業で今この瞬間も起きている恐ろしい現実があります。営業担当者が顧客リストをLLMサービスに貼り付けて分析を依頼し、エンジニアがソースコードをAIにデバッグさせ、人事担当者が従業員の個人情報を含む資料をAIに要約させています。これらの情報は一度外部のAIサービスに送信されれば、もう取り戻すことはできません。
LLM-Audit/PII Protectorは、このアウトバウンドリスクに対する究極の防御壁として機能します。従業員がどんなに無意識に行動しても、個人情報や機密データがAIに送信される瞬間を捉え、自動的にマスキングまたはブロックします。氏名、住所、電話番号といった基本的な個人情報から、クレジットカード番号、医療情報、さらには「部外秘」「Confidential」といったキーワードを含む文書まで、高精度AIが瞬時に検出し保護します。
インバウンド防御:AIの危険な出力から組織を守る
一方で、AIから返ってくる情報にも大きなリスクが潜んでいます。AIが生成した誤情報や不適切なコンテンツが、そのまま顧客への回答や経営判断の材料として使われれば、企業の信頼性は一瞬で崩壊します。実際に、AIチャットボットが誤った情報を提示して数千万円の損失を出した事例や、うっかり差別的な表現を含む文章を公開してしまい炎上した事例は枚挙にいとまがありません。
LLM-Audit Inbound-Guard は、このインバウンドリスクに対する包括的な監視システムです。AIが生成するすべての出力をリアルタイムで記録・分析し、問題のあるコンテンツを即座に検知します。不適切な表現、コンプライアンス違反の可能性がある内容など、多角的な観点から出力を評価し、必要に応じてアラートを発信または自動的に修正・ブロックすることができます。
まとめ:信頼できるAI時代の実現に向けて
ガーディアンエージェントは、AIの可能性を最大限に引き出しながら、そのリスクを適切に管理するための重要な技術です。企業がAIを安心して活用し、イノベーションを加速させるためには、この「デジタルの番人」の存在が不可欠となるでしょう。
しかし、ガーディアンエージェントの本格的な実装を待つ間にも、AIリスクは日々拡大しています。今こそ、企業は今すぐ実践できるLLMセキュリティから始めましょう。
以下は動画版としてガーディアンエージェントについて解説しています、あわせてご覧くださいませ
LLM-Audit のご紹介
当社は、LLMサービス開発・運営を通して得た経験・知見を集めた LLM防衛ソリューション 「LLM-Audit™」をご提供しています。
LLM-Auditは、まさに「今使えるガーディアンエージェント」として、企業のAI活用を即座に、そして確実に守ります。アウトバウンドでは機密情報の流出を防ぎ、インバウンドでは危険なAI出力から組織を保護する。この双方向の防御により、企業は安心してAIのイノベーションを推進することが可能です。
これにより、悪意ある入力プロンプトのブロック、LLMによる不適切な出力の監査を強力に実行しLLMの安全、安心を実現することができます。
OpenAI API 互換サーバーとして貴社LLMをラッピングするだけで利用できますので非常に小さな導入コストで高度化したLLMセキュリティを実現することが可能です。
LLMセキュリティやLLM-Audit™ にご関心がおありの場合は以下までご連絡くださいませ。またLLMセキュリティコンサルティングや製品デモについてもどうぞお気軽にこちらのお問い合わせフォームまでご連絡くださいませ。






